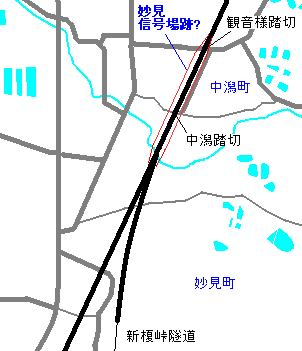
かつてこの区間は山裾に沿って線路が敷かれていた。そのため、カーブがきつい上に土砂崩れも時々起こった。そこで複線化を機に直線化され旧線は廃止された。新線の走っている所は水田で鉄道建設の障害になるような所ではないのに、なぜはじめから直線にしなかったのか不思議である。田んぼをつぶすのを避けるためだったのだろうか。
昭和42年編集の5万分の1地形図には、「国有鉄道は昭和42年9月現在」との注意書きとともに新旧線の両方が記載されている。
上越線の複線化は段階的に行われ、この付近は次のように進められていった。
・1962(S37) 11/29
小千谷〜越後滝谷間に妙見信号場新設
妙見〜越後滝谷間複線化
・1966(S41) 4/5
新榎峠隧道貫通
・1967(S42) 9/1
小千谷〜妙見信号場間複線化
妙見信号場廃止
これによると、複線と単線の境に一時的に妙見信号場が存在したようであるが、位置がはっきりせず、痕跡もない。新榎峠トンネル貫通前なのでそこより北であろう。小千谷と越後滝谷からの距離で判断するとトンネル手前の分岐点付近である。付近の方の話では、下の地図に示した位置にかつて駅ができる計画があり、そこは国鉄の用地だったが、結局駅はできなかったということだ。しかし列車がここでよく信号待ちをしていたという記憶があるということなので、ここが信号場跡ではないかと思われる。ただここの地名が中潟町というのが気になるが。
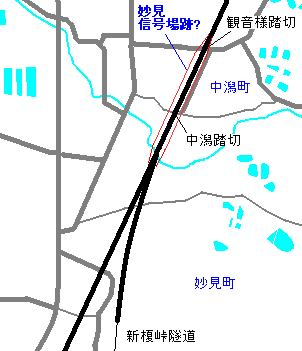


観音様踏切(近くに中潟観音があるため)の北側と南側。小道に沿って境界標が残り、その西は畑などになっているが線路側はJR所有のためか荒地のままである。
(2008.6)

上り線側脇に小道が通っている。近所の方の話ではその中心線上までが国鉄用地だったそうだ。
(2008.6)


中潟踏切南側。1枚目写真右に線路から離れて境界標が並ぶのが見える。
(2008.6)